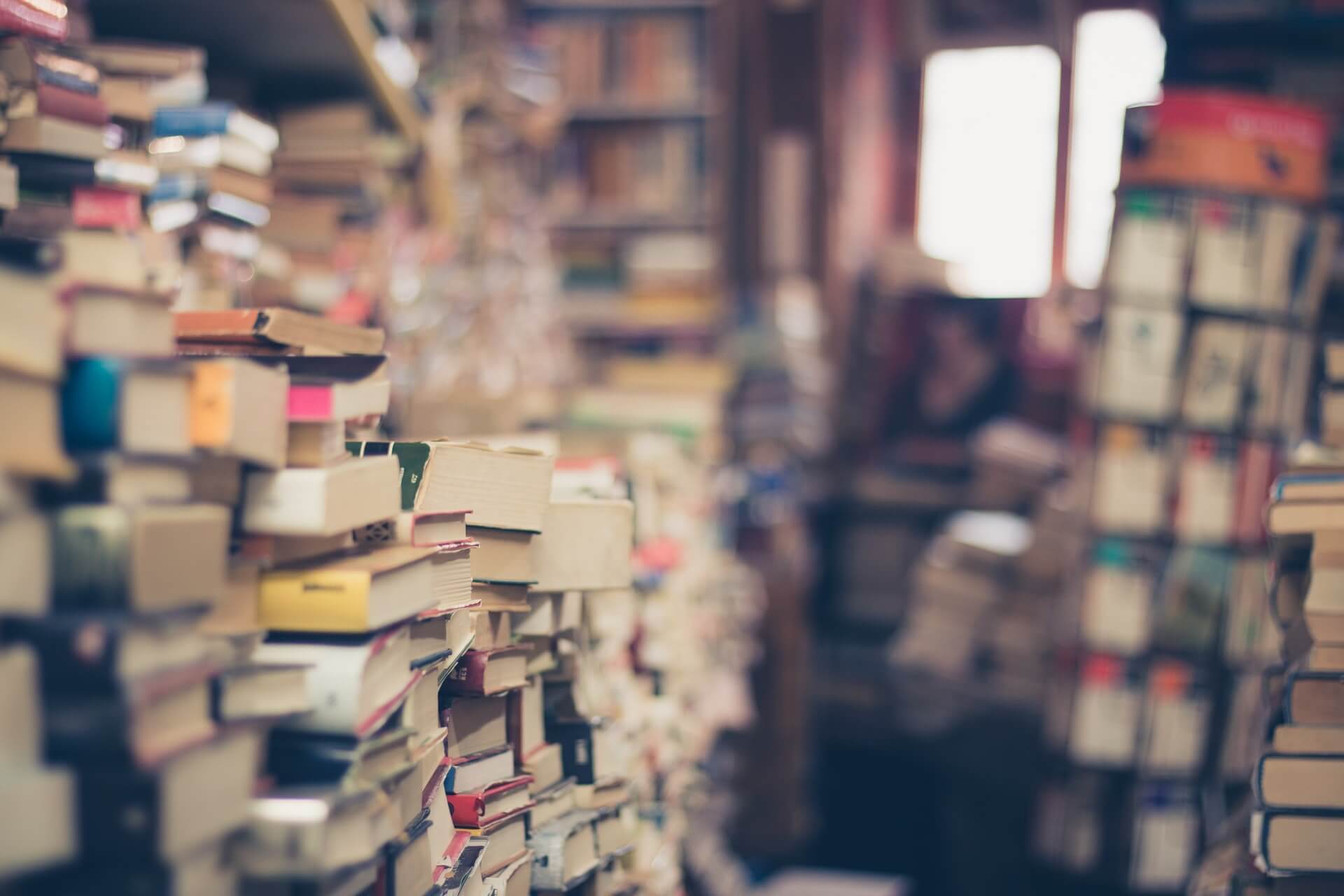
日本人が英語を話したり書いたりするときには、外国語であるが故に多くの誤りをおかします。しかし、英語を上達させたいと真剣に思うなら、間違えないようびくびくしているよりも、積極的にどんどん間違えて、逆にそれらを突破口に正しい英語に一歩でも二歩でも近づくようにすることが大事です。
この記事では、英語初心者~中級者の方が使い方を間違えやすい英単語を取り上げました。
今回はPART.2になります。
これらの英単語の基本的な意味、使い方のポイントをコンパクトにまとめています。
よく使われる英単語が多いので、一通りチェックしていただき、あなたの英語学習に役立てて下さい。
join
join『動詞』 ~を結合する、~と合流する、~に参加する
× I want to join to a tennis club here.
○ I want to join a tennis club here.
ここのテニスクラブに入りたいです。
【join】 もともとは「直接触れ合うように結びつける」という意味の語で「join the two pipes together」(2本のパイプをつなぐ)のように使います。
「人や団体に加わる、参加する」という意味を表す場合は、joinの後に前置詞は必要ないのですが、「~に入る」の「~に」に引きずられてついtoをつけてしまいがちです。
通常は「His brother joined the opposing team in town.」(彼の兄は市内にある相手チームに入った)や「Could I join you?」(ごいっしょしてもよろしいですか?)のように他動詞として、直接、人や団体などの名詞を後続させることになっています。
ところがこのjoinには、「(活動中の)人々に加わる」という意味の「join in」という句動詞があり、これも比較的よく使われるのでややこしいことになります。この場合は、しっかりとした組織などではなく、「一時的に活動している人の集まりに加わる」という限定があるので区別するようにしましょう。
例えば、「join in the Bon festival dance」(盆踊りの輪に加わる)や「We all joined in the chorus.」(みんなで一緒にコーラスを歌った)のように使われています。
fix
fix 『動詞』 ~を決める、修理する、仕組む
× The repairman fixed up the television set yesterday.
○ The repairman fixed the television set yesterday.
その修理工が昨日テレビを修理してくれた。
【fix】 もともと「締める、固める」の意味で、この意味では主にイギリス英語で使われます。「目指した場所や状態に固定する」が基本のイメージです。
使用頻度の高い単語で、多様な意味で使われますが、私たち日本人は「固定する」の意味で限定的に使用しがちなので、「(時間・場所・値段など)を決める」「修理する」「(髪など)を整える」「(食事・飲み物など)を用意する」「~を仕組む、裏工作する」といった意味も押さえておきましょう。
このうち、「修理する」「食事を作る」の意味で、set up(準備する)からの連想か、誤り文のようにupをつけてしまうケースが少なからずありますが、upは必要ありません。「テレビを修理してもらった」という意味で、「We had our TV set fixed yesterday」のように言うこともできます。
apply
apply 『動詞』 適用される、当てはまる、申し込む、~を適用する、塗る
× The same rule is applying to everyone.
○ The same rule applies to everyone.
同じルールが全員に当てはまります。
【apply】 ap「~に」+ply「くっつける」からできた語です。applyには「(規則や法などが)(人や事に)当てはまる」という意味がありますが、この場合は「当てはまっている状態」を表しており、進行形にはできません。
また、「apply for(~に応募する、申請する)」の形でも、「apply for a job as a waiter(ウェーターの仕事に応募する)」、「apply for a passport(パスポートの申請をする)」のようにしてよく使われます。
日本人にはあまりなじみのない意味に「(薬・塗料など)を塗る」がありますが、「Apply a thin layer of wax to~(~にワックスを薄くのばして塗って下さい)」といった形で、日常生活ではよく使われています。
派生語のapplicant(応募者)やapplication(応募、申込書、適用、塗布)もよく使われる重要語です。
share
share 『動詞』 ~を分ける、共有する 『名詞』 分け前
× My friend shared me the kitchen.
○ My friend shared the kitchen with me.
友人は私とキッチンを共有していた。
【share】 shareはもともと「分割」「分割して共有する」という意味を表します。カタカナ言葉でも「シェアする」「シェアNo.1」といった言い方をするので、私たち日本人にはなじみのある言葉でしょう。
シェアするものは、部屋などの「場所」、道具やおもちゃなどの「物」、さらには責任のような抽象的なものにもなります。また、シェアしたものを「分配する」ときにも使われます。
私たち英語学習者は、共有する相手を間接目的語のように並べてしまう誤りが多く、正しくは<share+物+with+人>「~を人とシェアする、共有する」の形になります。
「claim one's shares」(分け前を要求する)のように名詞としても使われます。
自分だけ得をするように分配することを意味する「lion's share」という表現もついでに覚えておいてください。
prepare
prepare 『動詞』 (~を)準備する、用意する
× As a presenter,I have to prepare the annual meeting next week.
○ As a presenter,I have to prepare for the annual meeting next week.
発表者として来週の年次ミーティングに向けて準備をしなければならない。
【prepare】 このprepareは、何か特定のものを準備するときにも、何かに対して備えるというときにも使える動詞です。
前者は直接目的語をとったうえでforなどを用いて備える対象を示し、後者は直接目的語をとらずにforなどを用いて備える対象を示します。例えば、前者は「He prepared a meal for me」(彼は私のために食事を用意してくれた)、後者は「Prepare for the typhoon」(台風に備えなさい)のように使います。
ただし、ときに微妙な意味の違いが生じて間違えることがあります。プレゼンする人が会議の発表に向けて準備するのであれば、「prepare for the annual meeting」としなくてはいけません。
forが入らなくても文法的には間違いではありませんが意味が違ってきます。当日の会場の設営など、会議を準備するのであれば、「prepare the annual meeting」でいいわけです。
doubt/suspect
doubt/suspect 『動詞』 ~でないと疑う/~であると疑う
× I doubt that he stole it.
○ I suspect that he stole it.
私は彼がそれを盗んだのではないかと疑っている。
【doubt/suspect】 doubtの語源はdouble(二重の)と共通で「2つの心を持つ、いずれを選ぶか迷う」、またsuspectはsu-(下から)+spect(見る)からできた語です。
このdoubtは「(後続の事実)を疑う、(後続の真否)を~でないと思う」という意味で、「I doubt that he stole it」というと、「彼がそれを盗んだという話を疑う、信用しない」、つまり「彼は盗んでいない」と思っていることになります。その意味でこの語は、「そうではないのではないか」という否定的な意味合いの語です。
なお、thatの代わりにifやwhetherも使われますが、thatは特に後続の文の内容に不信感が強いときに使われ、そうでない場合にはifやwhetherが使われています。日常生活での使用頻度比率はthatが50%、ifが40%、そしてwhetherが10%です。
これに対し、suspectは逆に、「本当にそうなのではないか」という肯定的な意味合いになります。したがって「I suspect that he stole it」というと、彼に対する盗みの嫌疑を肯定する見解になります。つまり、「疑わしい」と思っているわけです。そのような「被疑者」のことを名詞でsuspectと呼びます。
suggest
suggest 『動詞』 ~を暗示する、それとなく言う、提案する
× He suggested Bill the idea.
○ He suggested the idea to Bill.
その考えをビルに提案した。
【suggest】 sug「下へ」+gest「持ち出す」からできた語です。「提案する」という意味で、類語にproposeがありますが、proposeが積極的な提案であるのに比べ、suggestはより控えめな提案をあらわします。
suggestでポイントになるのは語法です。以下の点に注意しましょう。
①目的語に動名詞はとるが、不定詞はとらない。
②that節をともなう場合、このthatはしばしば省略される。また、that節内のshouldは省略されることが多い。
③誤り文のような目的語を2つとるいわゆる第4文型では使えない。(suggest+目的語+to+人)の形のみが使われる。
名詞形のsuggestion(提案)も、「make a suggestion(提案する)」、「at someone's suggestion(~の提案で)」などの形でよく使われます。
prove
prove 『動詞』 ~を証明する、(~であることが)判明する
× His explanation was proved to be right after all.
○ His explanation proved to be right after all.
結局は彼の説明が正しいと判明した。
【prove】 proveはもともと「テストする」という意味で「~を証明する」が基本語義です。
proveは直接目的語をとったり、that節をとったりと、比較的使い勝手のいい動詞ですが、使用頻度が高い割に日本人がなかなか使いこなせない形に「A prove to be~」「(Aが)~であると明らかになる、判明する」があります。
例えば、「 Ken proved to be a very nice father」(ケンはとてもいい父親だということが判明した)という文がその例になります。「証明された」と考えて受け身にしてしまいがちですが、「prove to be~」の形には、実際にいい父親ぶりを発揮することで「結果として証明することになった」というニュアンスがあるため、能動態のままでなければいけません。
この文は「Ken proved that he is a very nice father」と言うこともできますが、これだと既に事実としてあったことを証明してみせた、という感じになります。
まとめ
いかがでしょうか。今回は初心者~中級英語学習者が使い方を間違えやすい単語を取り上げました。
英単語に対して日本語の意味も単体で覚えてしまうと、上記のような勘違いをしがちですが、冒頭にも書いたように、英語を上達させたいと真剣に思うなら、間違えないようびくびくしているよりも、積極的にどんどん間違えて、逆にそれらを突破口に正しい英語に一歩でも二歩でも近づくようにすることが大事です。
どんどん使って、間違えて、訂正してを繰り返し、継続していけばあとは自然と正しい使い方が身に付いていくものです。無理をせず、あなたのペースで英語学習を継続していきましょう。
初心者~中級英語学習者が使い方を間違えやすい単語【PART.1】もあります。よろしければ読んで下さい。
-

-
初心者~中級英語学習者が使い方を間違えやすい単語【PART.1】
続きを見る